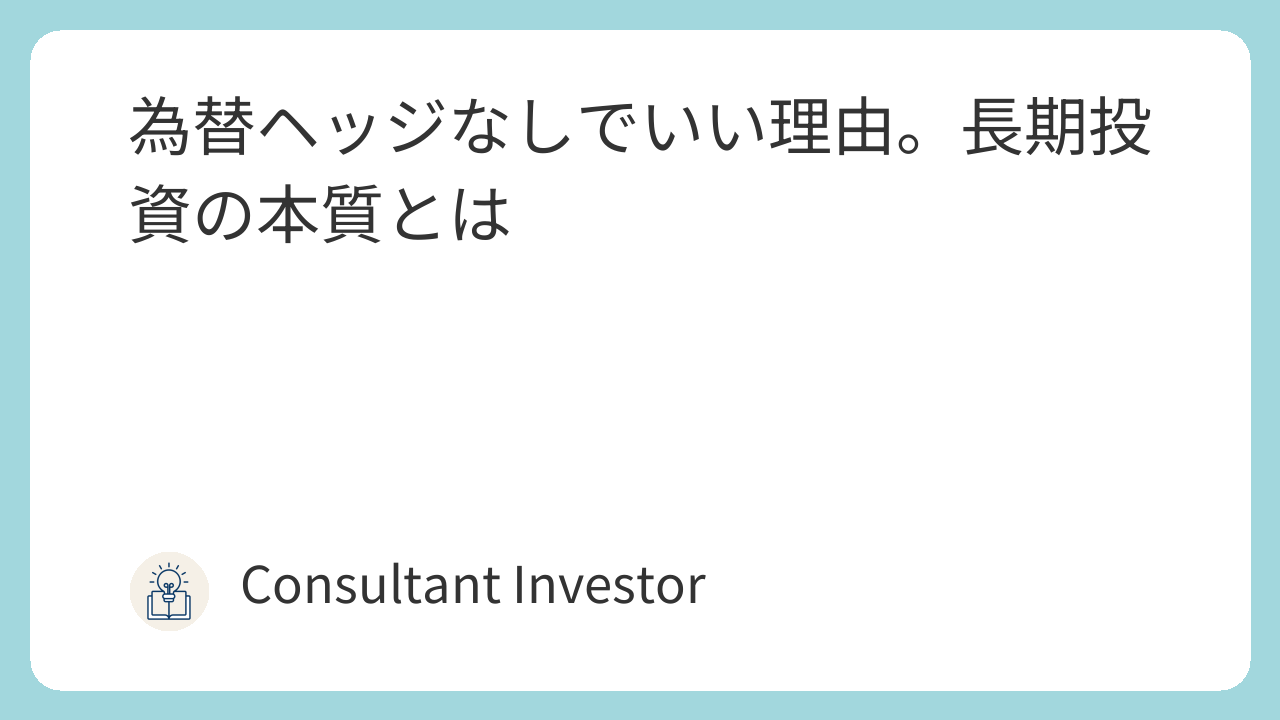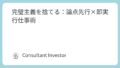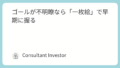「外国株の投資信託、ヘッジありとなし、どっちがいいの?」 長期投資初心者が直面するこの疑問。実は“為替ヘッジなし”という選択が合理的であるケースが多いのです。本記事では、為替リスクを正しく理解し、長期投資の本質に立ち返って最適な判断ができるよう、理論と実例をもとに解説します。
1. 為替ヘッジのコストと限界
為替ヘッジとは、為替の変動による影響を避けるために為替取引を行う仕組みです。しかし、このヘッジには「金利差コスト」がかかります。たとえば米ドル建て資産を日本円でヘッジする場合、アメリカと日本の金利差に応じてヘッジコストが発生します。
2020年代以降、日本の超低金利と米国の高金利が続いた影響で、ヘッジコストは年率1〜2%以上になることもあり、これがリターンを大きく圧迫します。つまり、ヘッジあり商品は「安全そうに見えて、実は割高」という可能性があるのです。
2. 長期投資と為替変動の関係
為替は短期的には読めません。ニュースや地政学リスク、金利政策などに反応し、数ヶ月単位で大きく変動することがあります。しかし、長期的には「平均回帰」の傾向があるとされ、一定のレンジ内で収束するケースも多く見られます。
加えて、日本円の実質購買力平価や経済成長率の観点から見ると、長期的には円安基調が続く可能性も指摘されています。これは、日本円で運用する日本人にとって、外貨建て資産の価値が円換算で高まる“追い風”になります。
3. 実績が示す“ヘッジなし”の優位性
たとえば、人気の投資信託「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」や「先進国株式インデックス」では、為替ヘッジなしの方が長期的に高いリターンを記録しています。
特に、2022年〜2023年の円安局面では、円ベースでの評価額が押し上げられ、想定以上の運用益を得た投資家も少なくありません。こうした実績が、為替ヘッジなしの合理性を実証しています。
4. 「為替リスク」は“持つ”ことで減らせる
為替リスクを避けようとすると、かえってコストがかさみ、長期のパフォーマンスを下げることになります。一方で、「リスクを受け入れる」姿勢で広く分散された資産に投資すれば、通貨リスクは時間と分散によって平準化されていきます。
インデックス投資の本質は「広く世界に投資すること」。つまり、複数の国・通貨・市場にまたがることで、為替の一方向のリスクを和らげることができるのです。為替は“排除”ではなく“取り込む”ことでむしろ味方にできるのです。
まとめ
長期投資においては、為替リスクを過度に恐れる必要はありません。 むしろ、「為替ヘッジなし」の投資信託を選ぶことで、低コストで世界の経済成長に乗ることができます。短期の変動に一喜一憂するよりも、時間と分散を味方にした運用が資産形成の王道です。
為替を読むのではなく、世界経済の成長に投資する──それがインデックス投資の本質です。