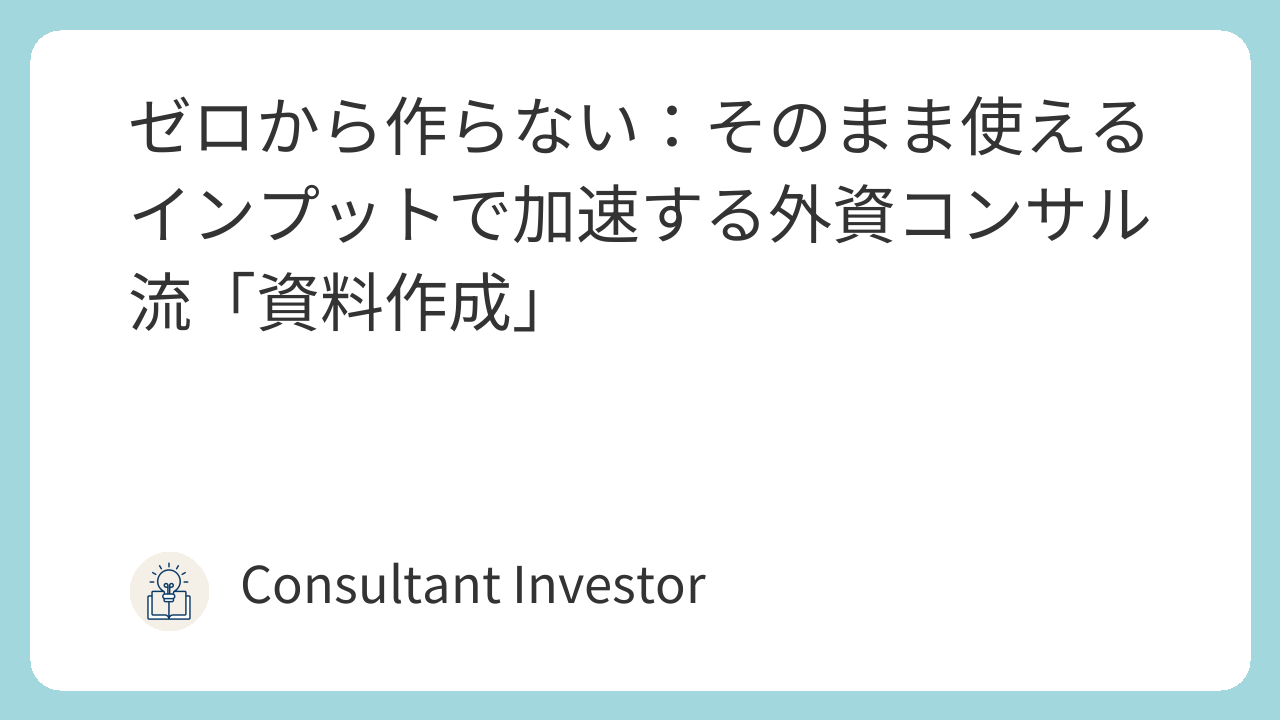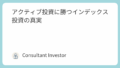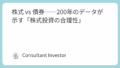外資コンサルの資料作成は「ゼロからつくらない」が鉄則です。最初にそのまま使える一次素材を大量に確保することで、スピードと品質を同時に実現します。本記事では、提案書やディスカッションペーパーなどをどう収集・活用し、効率的に成果物へつなげるのかを解説します。
社内資産を最優先に収集する
資料収集の優先度は、まず社内資産>外部調査>追加取材の順です。社内にはすでに活用可能な「提案書」「ディスカッションペーパー」「オファリング資料」などが豊富に存在します。これらは即転用できるため、最短で骨格を作るうえで欠かせません。外部調査や取材は、社内資産で補えない部分を補強する目的で使いましょう。
骨格を固めてからギャップだけ深掘り
効率的な資料づくりの流れは「骨格→肉付け」です。既存資料をもとにアジェンダを確定し、内容の大枠を早い段階で完成させます。その後に残るギャップ部分のみを追加調査で深掘りすれば、不要な調査を省きながらも説得力のある資料が仕上がります。
出典・数値・用語を統一して品質担保
既存資料をそのままコピペするだけでは「雑さ」が目立ちます。そこで重要になるのが出典明記・数値再計算・用語統一の三点セットです。たとえば数値は最新データに更新し、専門用語はチームで統一したガイドラインを適用するだけで、仕上がりが一気に洗練されます。こうした軽量なルールを用意しておくことで、再利用感を消しつつ高品質なアウトプットを実現できます。
再利用性を高める検索・保管の型
インプットは一度使って終わりではありません。再利用を前提に、ファイル命名のルール化と共通リポジトリの整備を行うことが重要です。例えば「YYYYMM_案件名_テーマ」といったキーワード命名を徹底し、チーム全員がアクセスできる場所に格納すれば、次回以降の調査や資料作成が圧倒的に早くなります。
まとめ
外資コンサル流の資料作成は、徹底して効率と品質を両立させるプロセスです。
- 社内資産を最優先で収集
- 骨格を先に固め、ギャップだけ深掘り
- 出典・数値・用語を統一して品質担保
- 命名規則と共通リポジトリで再利用性を確保
つまり、「集める→選ぶ→型に流し込む」の三段構えで進めることで、スピードと正確性を同時に実現できます。明日からの資料作成に、ぜひ取り入れてみてください。