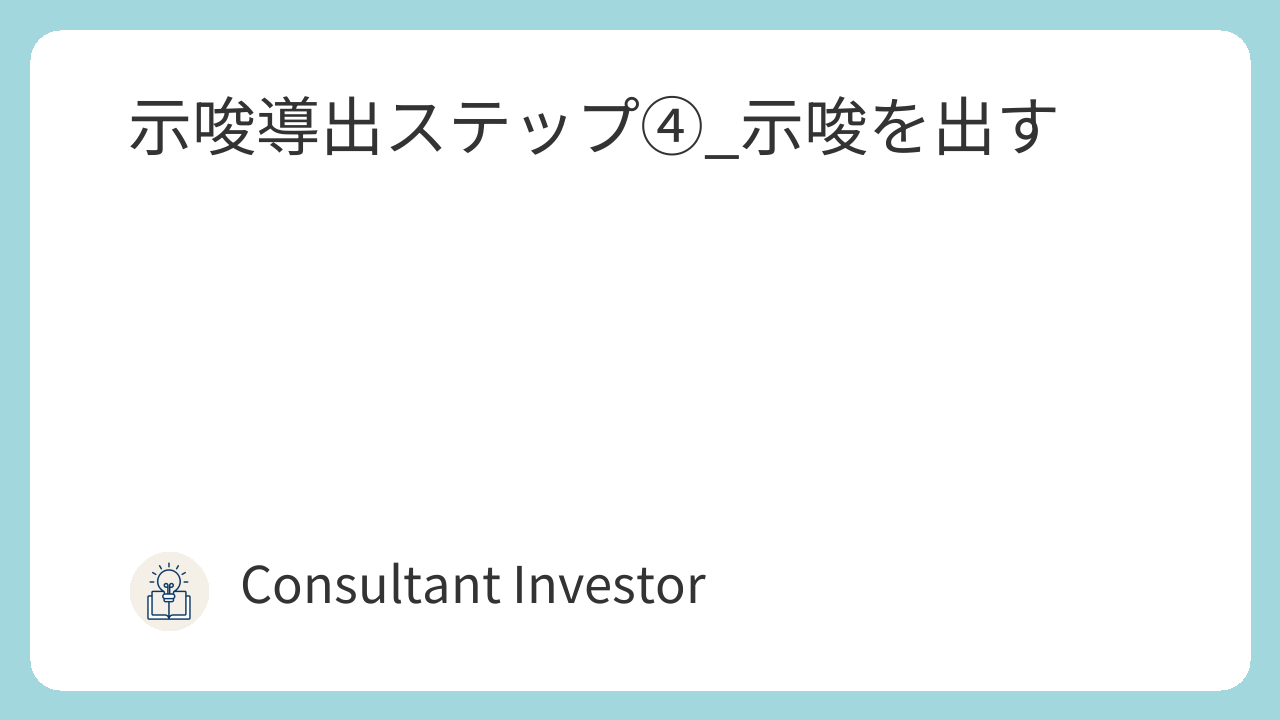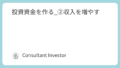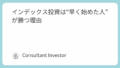「で、結局、何が言いたいの?」
この一言に詰まってしまう経験は、多くのビジネスパーソンが一度は通る道です。特に、外資コンサルや企画系の仕事では日常茶飯事。
大量に情報を集め、整理もしたのに、なぜか上司やクライアントの反応はいまいち…。その最大の原因は、「意味づけ」の不足にあります。
情報を集めることと、そこから示唆を出すことは、全く別のスキルです。 この記事では、コンサル実務で再現性高く使われている思考法を紹介します。これは情報整理の先にある「考える力の型」です。
「示唆」とは?
示唆の定義
示唆とは、「情報から相手の行動を導くメッセージ」です。単なる事実や感想ではなく、「だからどうする?」に答える考えのフレームそのもの。
■なぜ示唆が求められるのか?
ビジネスシーンでは、情報を提供するだけでは十分ではありません。相手の次の行動を後押しする「意味と方向性」が求められます。
このとき重要なのは、「事実 → 意味 → 行動」という流れをつくることです。
■良い示唆の3条件
| 条件 | 意味 | 効果 |
|---|---|---|
| 行動直結性 | 具体的なNext Actionが見える | 動きやすい |
| 筋道のある論拠 | Whyが語れる | 納得しやすい |
| 判断軸 or 選択肢 | 比較や意思決定の支援 | 応用しやすい |
示唆が弱くなる典型パターンとその原因
■パターン1:情報の羅列だけ(報告型)
「各部門の施策と実績はこの通りです」
→事実の提示だけで、考察ゼロ。
■パターン2:調査報告止まり(一般論型)
「世の中では●●の取組が有効とされています」
→汎用的すぎて、自社への接続が弱い。
■パターン3:評論止まり(指摘型)
「この状況は望ましくないと考えられます」
→行動案が提示されない。
情報を「示唆」に変える4ステップ
ステップ1:情報を論点別に再構造化する
- 情報は集めただけでは武器にならない
- 仮説・論点ごとに再整理する
- 因果・背景・影響に分けて並べ直す
ステップ2:So What?(だから何?)を言い切る
- 相手が求めているのは「何が言いたいか」
- 1行で仮メッセージを立てる
- 最初はざっくりでもOK
ステップ3:Why So?(なぜそう言える?)を支える
- So Whatの根拠を用意する
- 定量/定性/現場の声のセットで考える
- 情報の配置で説得力が変わる
ステップ4:What Next?(次にどうする?)を提示する
- 行動案 or 判断軸を渡す
- 短期・中長期での切り分けも有効
- 選択肢ベースでも良い
示唆出しの実践Tips
■相手の視座に合わせた示唆を考える
| 相手 | 求められる示唆 |
|---|---|
| 経営層 | 意思決定・判断支援 |
| マネージャー | 施策の具体提案 |
| 現場担当 | 実行方法や工夫の案 |
■複数の示唆案を出す
- チームで発散→収束が王道
- 1案に頼らない
- 別解・逆張り・補助線思考
まとめ
示唆とは、情報から「意味」と「行動」を生み出す技術です。
- 情報を論点別に再構造化
- So What?を言い切る
- Why So?で支える
- What Next?を提示する
この流れは、単なるコンサルスキルではなく、全てのビジネスパーソンに必要な「考える型」です。情報を集めて終わりではなく、そこから価値を生み出す。それが、プロフェッショナルとしての思考法。
あなたもぜひ、明日からの現場で活用してみてください。