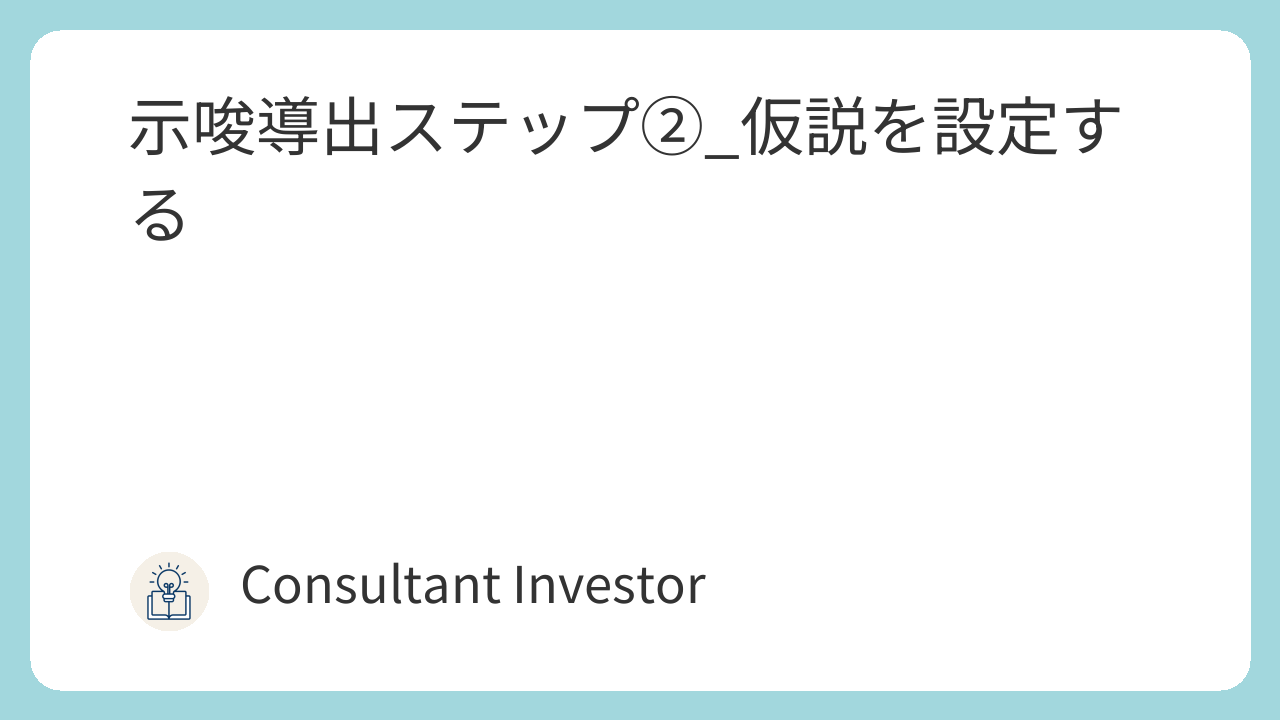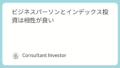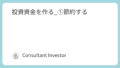コンサルティングの現場では、「アウトプットは決めたけど、その後どう進めればいいかわからない」という声をよく聞きます。その疑問に対する答えが、仮説を置くことです。
ここでの仮説とは、“勘に頼る仮の結論”ではなく、思考を進めるための仮の構造やメッセージ。 つまり、結論を急ぐのではなく、「何を検証すべきか」「どこから考え始めるべきか」を明確にするための指針です。
この記事では、示唆導出プロセスの第2ステップとして、仮説をなぜ置くのか、どう置くのかを実務フレームで分解して解説します。
そもそも仮説とは何か?
仮説は「検証すべき論点の仮置き」である
ここで定義する仮説とは、最終的に出すべき成果物の「構成」や「中身」に対する、仮の答えや主張です。重要なのは、“正しいかどうか”ではなく、“どこから考えるか”という起点になること。たとえば、業務改善のプロジェクトでは以下のような仮説が置かれます。
- 課題仮説:「業務が属人的で処理時間にばらつきがある」
- 解決策仮説:「業務手順の標準化とKPI再設計が必要」
- 実行仮説:「改善余地の大きい領域から段階的に導入すべき」
このように仮説を持つことで、検証対象が絞れ、調査や分析が効率的に進むようになります。なお、これは戦略系・業務改善系のプロジェクトで特に有効ですが、定量分析を主とするリサーチ業務や定型タスクでは相対的に重要度は下がります。
なぜ仮説を置くと、プロジェクトが進むのか?
“仮説なき分析=迷子の思考”を避ける
仮説を置く最大の意義は、思考や行動の軸が生まれることです。以下の3つの観点で、その効果を期待できます。
■情報収集が目的ベースになる
→ 必要な情報と不要な情報を峻別しやすくなる
■分析設計が論点主導で明確になる
→ 仮説と照合する前提で、因果構造を意識した設計が可能になる
■関係者との認識合わせが早期にできる
→ 「仮にこう考えている」という提示で、意見を集めやすくなる
特に不確実性の高いテーマでは、仮説を起点にディスカッションが可能になり、初期の進行が格段にスムーズになります。
仮説を構築するための4ステップフレームワーク
① アウトプット構成を仮置きする(章立て)
最初に、最終成果物の構成を仮で描いてみることから始めます。これは思考のフレームを定義する作業です。
例:
- プロジェクトの背景と目的
- 現状分析
- 核心的な課題
- 解決策の方向性
- 実行ステップと効果見込み
この構成があるだけで、以降の論点整理や情報収集の方向性がブレにくくなります。
② 各章に“仮のメッセージ”を置く
構成が描けたら、それぞれの章に仮の主張(メッセージ)を記述します。
- 「現状分析」→ 属人化により業務の効率にばらつきがある
- 「課題」→ 業務設計とKPIが機能的に乖離している
- 「解決策」→ KPIを業務単位で再設計し、役割の再定義が必要
この段階での主眼は精度よりも思考の起点づくりです。 仮でも主張を置くことで、論点が形を持ち始めます。
③ 根拠・因果構造を仮置きする
次に、各メッセージに対する因果構造や背景要因を仮で整理します。
- 属人化の背景:マニュアル未整備、属人的ノウハウの蓄積、役割不明確
- KPI乖離の原因:現場業務とKPI設計の非同期、部門間の調整不在
この工程は、ピラミッド構造(主張→理由→事実)に沿った思考整理そのものです。 あとで検証するべき仮のメカニズムを先に置くことで、思考が深まります。
④ 検証すべき情報リストを作る
最後に、「この仮説を検証するには、どんな情報が必要か?」をリストアップします。 これは示唆導出の次のステップ(情報収集)に直結する行動指針になります。
例:
- 各業務の処理時間・担当者別の実績ログ
- 業務別KPIと実行タスクの対応一覧
- 属人業務の棚卸し(インタビュー・ログデータなど)
このように情報が明確化されると、調査設計やチームの分担もスムーズに進行します。
まとめ
アウトプットを定義したら、次に行うべきは”仮説を置く”こと”です。 それは、正しさを求めるのではなく、「どこから考え始めるか」を決める行為です。仮説を置くことで、
- 論点が明確になる
- 情報収集が目的志向になる
- 関係者との認識調整が早期にできる
という実務的な価値をもたらします。
そして、特に若手にとっては、「仮説を置き、検証して修正する」経験を積み重ねることが、将来的な論点設計力や構造化力の成長に直結します。