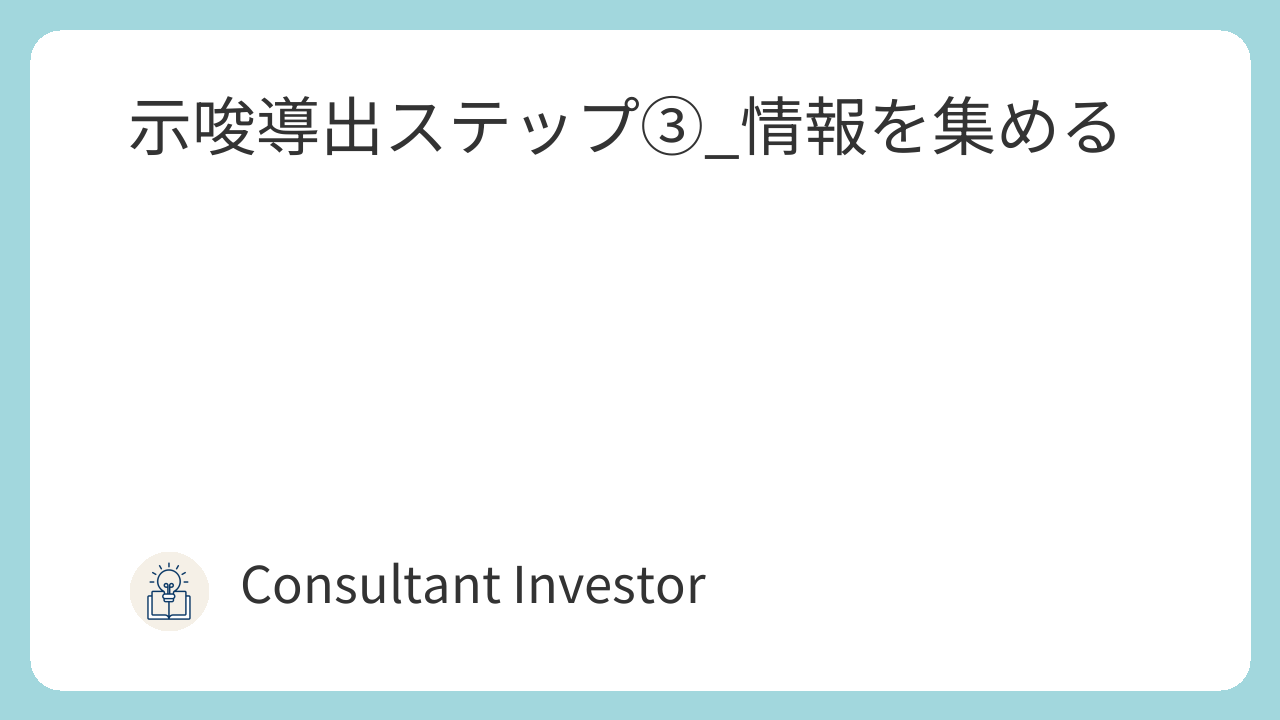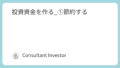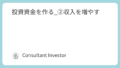「とりあえず情報を集めてみたんですが…何が重要で、何がいらないのか分からなくなってきました…」これは若手コンサルが現場でよく口にするセリフです。 一生懸命に動いたはずなのに、成果に繋がらない——そんな状況は珍しくありません。
でも、その原因はとてもシンプルです。——それは「調べる前に、調べる設計がないから」。
外資コンサルの情報収集は、行き当たりばったりではありません。 必ず「仮説」から逆算して、「誰に」「何を」「どう聞くか」を事前に緻密に設計します。
この記事では、情報迷子に陥らないための「情報収集設計」の考え方と、実践的なノウハウを解説します。
情報収集の目的は「仮説を検証すること」である
情報収集の目的は、決して「たくさん集めること」ではありません。 目的は一つ——「仮説を検証すること」です。
なぜなら、仮説があるからこそ、
- 必要な情報と不要な情報が峻別できる
- 情報探索の優先順位が決まる
- 行動計画が描ける
逆に、仮説がない状態で情報を集め始めると、
- あれもこれもと収集して疲弊
- 重要情報を取り逃す
- 収集が終わらない
といった典型的な「情報迷子」に陥ります。
外資コンサルの実務では、情報収集は「仮説ドリブンの行動設計」そのものです。
情報収集設計の3フェーズ
外資コンサルが実践する情報収集設計の基本フレームは、以下の3フェーズです。
■フェーズ1:何を集める?(検証論点のリストアップ)
まず最初にやるべきは、「検証したい論点」をリストアップすること。 これは示唆導出ステップ②(仮説設計)で整理した構成やメッセージに基づいて抽出します。
例:
- 業務が属人的か? → 各担当者の処理時間
- KPIが機能しているか? → KPI設計と実業務の対応状況
■フェーズ2:誰から・どこから集める?(情報源マップ)
次に、「誰が」「どこに」「その情報を持っているか?」を洗い出します。
- 社内資料(業務マニュアル・KPIデータ)
- 担当者インタビュー
- 過去プロジェクト事例
- 公開データ・調査レポート
この時点で情報の「入手難易度」や「優先順位」も考慮します。
■フェーズ3:どうやって集める?(ヒアリング・資料・データ計画)
最後に、具体的な取得方法を決めます。 特にヒアリングでは、質問リストの精度が成否を分けます。
質問は以下の順番で構成すると効果的です。
| 質問の順番 | 意図 | 例 |
|---|---|---|
| 事実 | 状況の確認 | 「この業務って、いつからこのやり方ですか?」 |
| 背景 | 理由・経緯 | 「なぜそういう手順になったんですか?」 |
| 意見 | 課題認識 | 「やりにくい・困っている点はありますか?」 |
情報収集における具体Tips
■ Excelメモは「論点×事実」で整理する
情報はそのままメモするのではなく、論点別に分けて、1行に1つの事実を書き出します。 シンプルですが、このルールだけで、後の思考整理が驚くほど楽になります。
| 列名 | 内容 |
|---|---|
| 論点 | 検証したい視点(例:業務の属人化) |
| 事実 | 観察された事実(例:処理時間が担当者で2倍差) |
| 情報源 | 入手元(例:処理ログデータ) |
| 備考 | 補足や仮説への影響など |
■easy winから着手する
情報収集は「簡単に取れるもの」から着手し、仮説を磨きながら次の行動を決めるのが鉄則です。
具体例:
- 社内共有フォルダの資料
- 過去のPJナレッジ
- FAQやQ&A履歴
これらを押さえてからヒアリングに行くと、質問の質が格段に上がります。
まとめ
情報収集は「とにかく集める」ものではありません。 「仮説を検証する行動を設計する」ものです。
そのためには、
- 検証論点を明確にする
- 情報源を洗い出す
- 行動計画を練る
- easy winから実行する
- 集めた情報は即整理する
この一連の設計と実行ができれば、情報は自然と集まり、質も深まります。
外資コンサル流の「情報収集設計」を実務に取り入れて、迷わない・ブレない情報収集を実践していきましょう。
行動が変われば、成果が変わる。情報収集も例外ではありません。