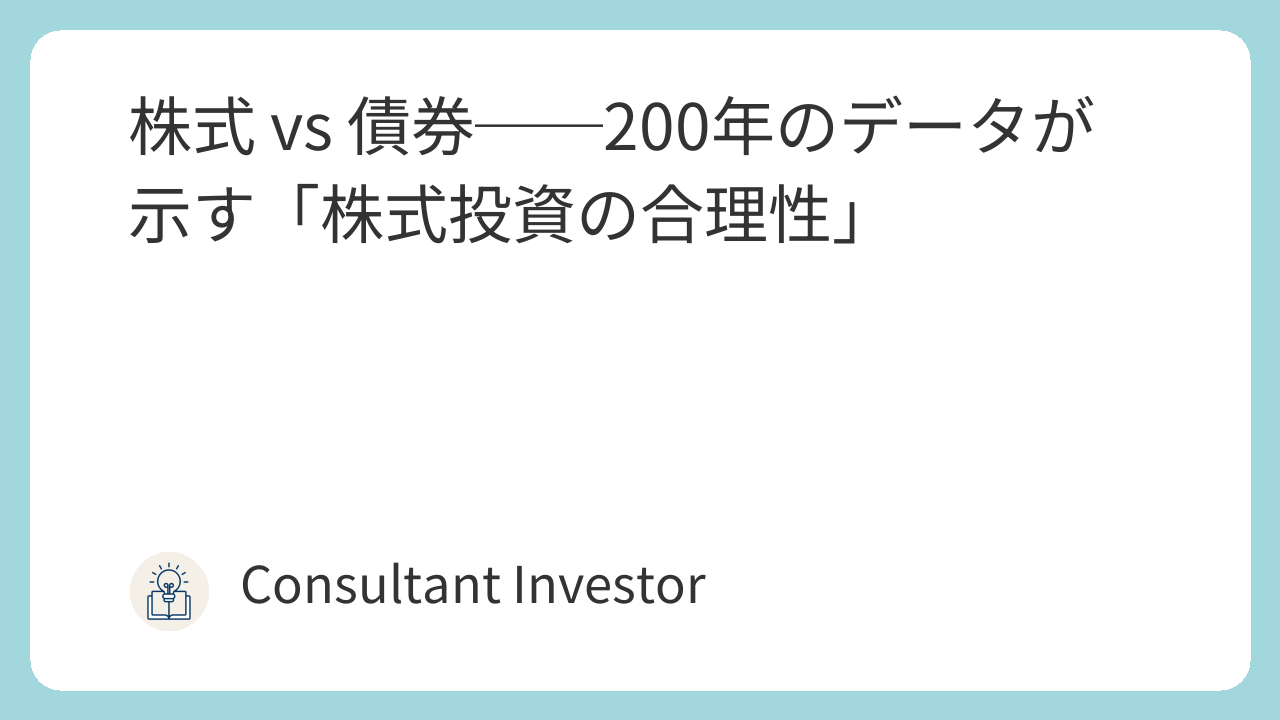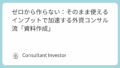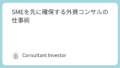資産形成に取り組む際、誰もが一度は迷うのが「株式」と「債券」のどちらを選ぶべきかという問いです。 安定性が魅力の債券か、成長性に期待できる株式か──。この論点に対して、過去200年以上のデータが明確な答えを示しています。 本記事では、長期的な視点から見た場合に、なぜ株式投資が合理的なのかを歴史的事実とインフレの影響を踏まえて解説します。
200年間のデータが示す株式リターンの優位性
米国の経済学者、ジェレミー・シーゲル教授の著書『株式投資』では、1802年から2006年までの204年間にわたる投資リターンが比較されています。 この研究では、以下のような驚くべき事実が明らかになっています。
- 株式の年平均実質リターン:6.8%
- 米国長期国債の年平均実質リターン:3.5%
- 米国短期国債の年平均実質リターン:2.8%
また、第二次世界大戦以降の戦後60年間(1946〜2006年)に限定しても、傾向は変わりません。
- 株式:6.9%
- 長期債:1.6%
- 短期債:0.6%
このように、どの時代を切り取っても、株式は債券を明確に上回るパフォーマンスを示しています。
インフレに弱い債券、強い株式
債券の低リターンの一因は、インフレの影響にあります。 債券は、あらかじめ決められた利率で利息を得る金融商品です。したがって、インフレが進行すると実質的な購買力が目減りし、リターンが大幅に削られます。
一方で、株式は企業の実体経済に基づく資産であり、企業が物価上昇に応じて価格や利益を伸ばせば、それに連動して株価も上昇します。 結果として、株式はインフレ耐性が高く、長期的に実質資産価値を維持しやすいのです。
特に戦後のインフレ期では、株式のリターンはほぼ変わらなかったにもかかわらず、債券は大きくリターンを下げました。これはインフレに対する債券の「脆弱性」を物語っています。
長期投資家にとっての意味とは?
インフレや市場変動という不確実性に立ち向かうためには、「長期」という時間軸を味方につけることが有効です。 株式は短期的には価格の上下が激しい資産ですが、長期で保有することでボラティリティが緩和され、リターンも安定してくる傾向があります。
さらに、分散されたインデックス投資──例えばS&P500やオールカントリーなど──を通じて株式市場全体に投資することで、個別リスクを抑えつつ、経済成長の恩恵を享受できます。
一方、債券の利回りは低いため、インフレリスクを考慮すると「資産を守る」用途には適していても、「資産を増やす」には向いていないと言えるでしょう。
まとめ:歴史が証明する「株式投資の合理性」
株式と債券の過去200年の比較から明らかなのは、長期的に見て株式は債券を凌駕するリターンを提供してきたという事実です。 インフレへの耐性や経済成長との連動性を考えると、株式は将来的な購買力の維持にも有利です。
短期的な価格変動に振り回されず、時間を味方に付けた「インデックス投資」を継続することで、誰もが資産形成の勝者になれる可能性があります。
あなたの資産形成は「未来の自分への投資」です。今こそ、長期的に合理的な選択を。