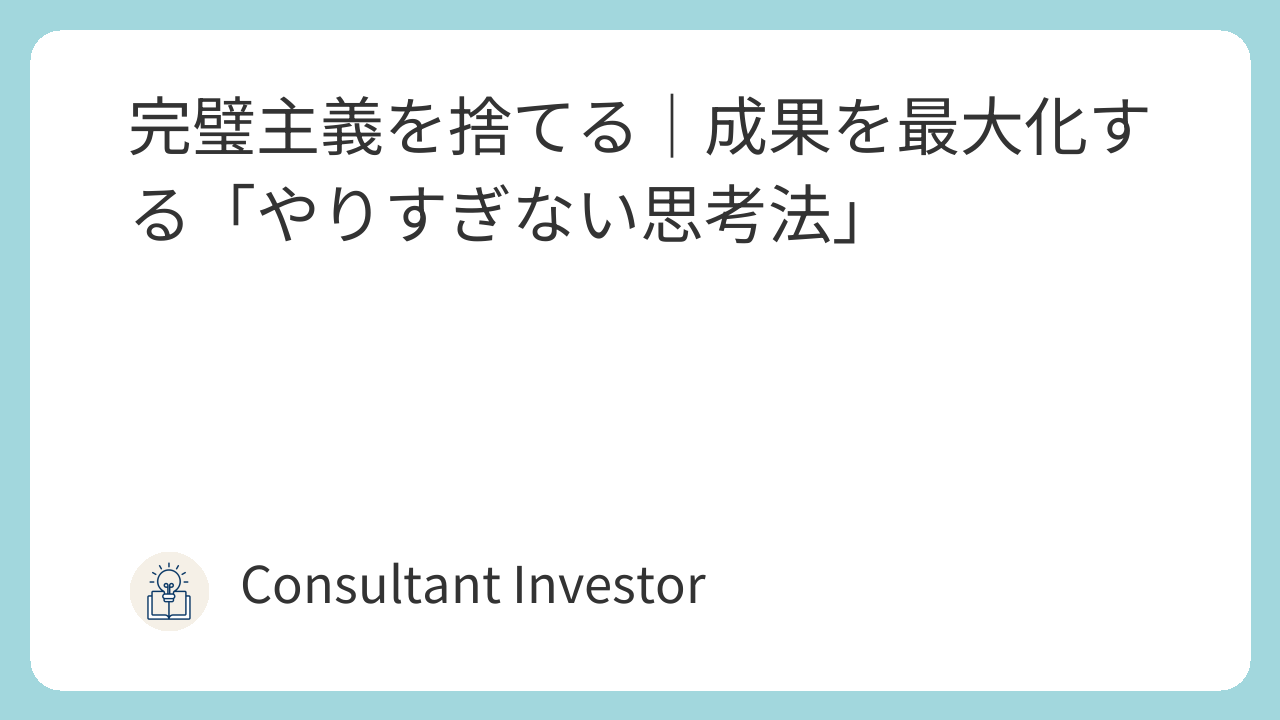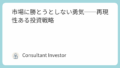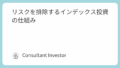「もっと良くできるはずだ」。その前向きな気持ちが、いつの間にか“完璧主義”にすり替わってしまうことがあります。
この“やりすぎ”が問題なのは、努力が目的化し、成果と結びつかなくなるからです。 外資系コンサルの現場では、「どれだけやったか」よりも”「なぜ、そこで止めたのか」という判断力”が重視されます。
本記事では、成果に直結する“やりすぎない力”を解説します。
1. 完璧主義が評価されにくい理由
完璧を目指す姿勢は一見誠実ですが、実務ではむしろマイナス評価になりやすいのが実情です。
なぜなら、ビジネスでは”「目的との整合性」が最優先されるから”です。いくら丁寧に作った資料も、意図や用途に合っていなければ無価値です。
特に、プロジェクト初期や議論のスタート段階では、「粒度を粗く、論点を明確にする」ことのほうが評価されます。 完璧主義はこのフェーズで“ズレた努力”を生みやすく、信頼を損なう原因になり得るのです。
2. 「必要十分な水準」を見極める3つの判断軸
「どこまでやるべきか」を迷うときは、以下3つの視点を使えば、過不足のない水準を設定できます。
① 誰に・何を・どこまで伝えるのか?
相手の立場・目的・時間感覚を踏まえて、どの論点をどの粒度で伝えるかを定めるだけで、やるべきことが明確になります。
この視点が抜けると、「万が一のために」と情報を盛り込み、本質をぼやけさせる非効率な完璧主義に陥ります。
② スコープと品質水準の事前合意
「ここまでやればOK」とゴールラインを握ることは、過剰品質を防ぐ最もシンプルな方法です。 それを超える作業は、誰のためにもなっていない“余計な正義”になることがあります。
③ 時間投資とリターンの釣り合いを測る
「この作業に1時間かけて、どれだけ成果が変わるか?」という問いを持ちましょう。 差分のインパクトが小さいなら、やめる判断が正解です。意思決定のスピードも価値の一部です。
3. 「やらない選択」が信頼に変わる理由
「やらない」は怠慢ではありません。むしろ、成果に向けて“選び抜く力”の現れです。
たとえば、「この資料は粗いですが、まず論点整理を優先しました」と説明できる人は、状況判断に長けたプロとして信頼されます。
信頼される人の特徴は、「なぜやったか」より「なぜやらないか」を明確に語れること。これこそ、成果に直結する“やりすぎない思考法”の核心です。
4. 現場の実例|「粗さ」が武器になった資料作成
あるプロジェクトで、クライアントに提出するプレゼン資料をあえて粗い構成で提示したことがあります。
全体の構成と論点のみを示し、表や図などの装飾はあえて入れませんでした。 その意図は、「まず論点に対してフィードバックをもらうこと」に絞っていたからです。
結果として、「考え方が明確」「議論しやすい」と高評価。方向性が早期に定まり、その後の作業スピードと品質が大きく向上しました。 削ぎ落とす判断が、逆に成果を引き寄せる実例です。
まとめ|やりすぎない判断が“成果と信頼”をもたらす
完璧を目指すのではなく、「この作業は、目的にとって十分か?」という問いを判断基準にしましょう。
- 誰のための作業か?
- 何のための作業か?
この2つが曖昧なときは、むしろ立ち止まって“やらない選択”を検討すべきです。
やりすぎないという判断は、あなたを「結果を出す人」に変える確かなスキルです。成果と信頼を両立させるために、今こそ“完璧より構造”という視点を持ちましょう。